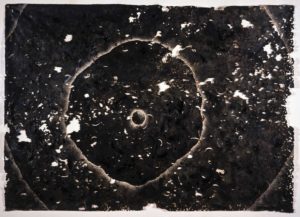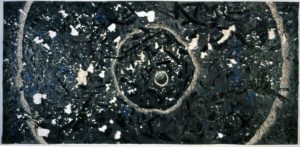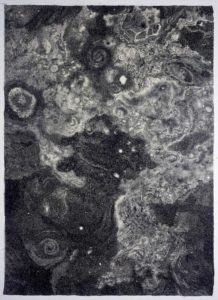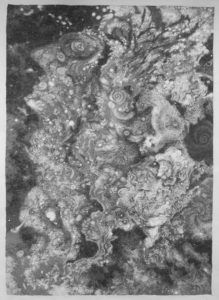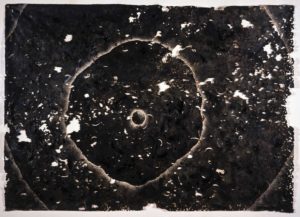
生まれた時から目の前にあった。
鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱
It’s Been Right Front of Me Since the Day I Was Born
Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper
152×213cm
1990

小さいと言い換えてもよいのではないか
鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱
In Other Words, Perhaps We Can Say This Is “Small”
Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper
212.5×442cm
1989
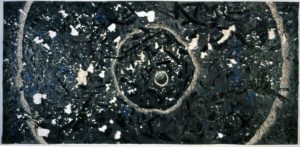
すべてがあらわになっている
鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱
Everything Is Revealed
Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper
212.5×442cm
1990

彼女は今しがた発った。
鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱
She Has Just Left
Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper
361×858 cm
1992

私の誕生
鳥ノ子紙にインク
The Beginning of Me
Black ink on Torinoko Japanese paper
214×154cm
1997

あなたの声を聴かせてよ
鳥ノ子紙にインク
Let Me Hear Your Voice
Black ink on Torinoko Japanese paper
214×154cm
1997

誰もが一人で死に至る苦しみに耐えなければならない
鳥ノ子紙にインク
Everyone Must Endure the Pain of Dying Alone
Black ink on Torinoko Japanese paper
214×154cm
1997

この世界の全死者に捧ぐ
鳥ノ子紙にインク
Dedicated to All the Deceased of This World
Black ink on Torinoko Japanese paper
213×153cm
1997-1998

とうてい理解しえない
鳥ノ子紙にインク
Can’t Get It at All
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
1998

視野は拡大されて
鳥ノ子紙にインク
The View Had Expanded
Black ink on Torinoko Japanese paper
213×153cm
1998-1999

1兆個の細胞が私をしている
鳥ノ子紙にインク
My 1,000,000,000,000 cells
Black ink on Torinoko Japanese paper
214×154cm
1998

今、母親が赤ん坊を産み落とした
鳥ノ子紙にインク
Just Now, the Baby Fell Out of the Mother’s Womb
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
1998-2007

絵画
鳥ノ子紙にインク
Kaiga (Painting)
Black ink on Torinoko Japanese paper
211×278cm
2000-2010
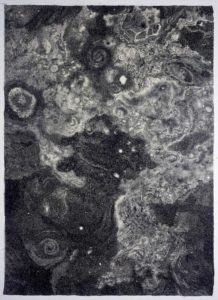
何度も何度も、ああ気持ちいいなと、、、。
鳥ノ子紙にインク
Again and Again, I Feel So Good
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
2000

お体に気をつけてください
鳥ノ子紙にインク
Please Take Care of Yourself
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
2000

時間はあのように使いたい。
鳥ノ子紙にインク
I Want to Spend Time Like That
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
2000

人は死ぬとどこへ行くのか
鳥ノ子紙にインク
Where Do We Go After Death?
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
2003

死スルコト 愛スルコト
鳥ノ子紙にインク
To Die and to Love
Black ink on Torinoko Japanese paper
213.5×153cm
2004-2005

皮膚は我々を拘束しているのだろうか それとも我々を抱きしめているのだろうか。
鳥ノ子紙にインク
Does Our Skin Restrain or Embrace Us?
Black ink on Torinoko Japanese paper
223.5×161cm
2005
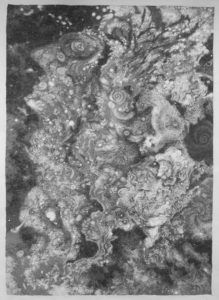
万物は流転する
鳥ノ子紙にインク
All Things Are in a State of Flux
Black ink on Torinoko Japanese paper
224×166cm
2009

あなたは死産児であった。
鳥ノ子紙にインク
You Were a Stillborn Baby.
Black ink on Torinoko Japanese paper
227×160cm
2013

凝縮をまねく
鳥ノ子紙にインク
Calling Forth Condensation
Black ink on Torinoko Japanese paper
226×166cm
2014

微笑から癇癪までの幅
鳥ノ子紙にインク
The Distance from a Faint Smile to a Fit of Anger
Black ink on Torinoko Japanese paper
224×160cm
2014

冷え切った図
鳥ノ子紙にインク
A Freezing Cold Painting
Black ink on Torinoko Japanese paper
220×161cm
2014

男の眼の中に庭が写っている
鳥ノ子紙にインク
A Garden in the Man’s Eyes
Black ink on Torinoko Japanese paper
226×160cm
2014

湧き出ずるところから
鳥ノ子紙にインク
From the Place Where Something Gushes
Black ink on Torinoko Japanese paper
224.5×161cm
2014

ここは何故あるのか
鳥ノ子紙にインク
Why Does This World Exist?
Black ink on Torinoko Japanese paper
226×160.5cm
2015

怒涛
鳥ノ子紙にインク
Surging Waves
Black ink on Torinoko Japanese paper
226×160.5cm
2015, 2017

事件
鳥ノ子紙にインク
Jiken
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×435.9cm
2006-2017

事件 (部分)
鳥ノ子紙にインク
Jiken (detail)
Black ink on Torinoko Japanese paper
…
…

もう始まってしまったここ
鳥ノ子紙にインク
It’s Here, Where Everything Started
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2015-2016

冬至 (地上からの透視図)
鳥ノ子紙にインク
Winter Solstice (A Perspective Drawing From Earth’s Surface)
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2018

固唾を吞む
鳥ノ子紙にインク
With Bated Breath
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152.5cm
2018

表われた事
鳥ノ子紙にインク
The Thing That Appears
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2018

画がけそうではない
鳥ノ子紙にインク
I Can’t Quite Depict
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2015-2016

極点
鳥ノ子紙にインク
Extreme Point
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2016-2017

嘲笑
鳥ノ子紙にインク
Ridicul
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2016

止揚
鳥ノ子紙にインク
Aufheben (Sublation)
Black ink on Torinoko Japanese paper
212×152cm
2017